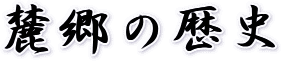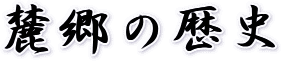|
1. 開拓の足どり(その1)
|
はじめに、麓郷の地名の由来についてお話します。北海道の地名はアイヌ語がもとになっているものが多いのですが、麓郷は違います。当時の東大演習林主任の「座間 孝雄」さんという人が、
「大麓山のふものと村だから、麓郷というのはどうだろう?」と考え、命名されました。
それまでは、布部演習林、または単に「布部」と呼ばれていたのです。ときに、大正13年のことでした。開拓から3年の年月が流れていました。
東大演習林の創設は明治32年です。麓郷は地元の人口が極めて少なく、演習林内に農耕に適した土地が5000ヘクタールもあったことから、林内殖民をすすめて労働力を得る方法がとられました。
さて、その演習林の開拓ですが、山部地区が明治40年、西達布地区が明治40年、布礼別が大正6年にそれぞれ開拓がはじまりました。麓郷の原始林に初めて斧が入れられたのは、1918年。大正7年のことでした。東大演習林の指導で、付近から300人もの労働者が投入されました。
やがて、1921年。大正10年。いよいよ、第1次農地払い下げ希望者を募集したところ、76名が願い出ました。この1921年をもって、麓郷の開拓の始まりとしています。
この76名の中には、本州からの人もわずかにいますが、主に道内からの入植者です。
「もっと広い農地がもらえて、うまくいきそうな土地があるぞ」との話を聞きつけてとなりの布礼別からやってきた、20名も含まれていました。
|
|
開拓の足どり(その2) |
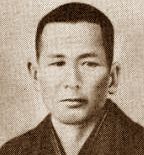
渡邊忠五郎氏
宮城県出身
|
開拓は、原始林の伐採に始まり、ササ刈り、火入れ、そして人力でたがやす、という果てしなく過酷な労働でした。原始林は、真昼でも暗いというような状態だったそうです。まずは、自分たちの食べるものを作らなければなりませんので、小麦、いなきび、そばなどを作りました。
米が作れるようになったのはもっと後のことで、大正13年。 西麓郷共生会館前において稲を耕作し、10アールの収穫があったのが、麓郷の稲作の始まりだということです。
入植者たちの住んだ家は、いわゆる「ほったて小屋」です。屋根は板ぶきで、壁は一重の板張り、床にはむしろが敷かれていました。入植してしばらくしても、畳の入っている家などほとんどなく、ゴザが強いてある家はゼイタクな方でした。
そんな中を、真っ先に開拓に取り組んだのが、渡邊忠五郎さんです。渡邊さんは、大正8年、三軒屋に一時入植しましたが、翌大正9年。座間孝雄氏より布部演習林貸下げのことを聞き、第一陣の入地を希望し、大正10年5月に草分けとして移住しました。
渡辺さんは「かげ、ひなたなく、誠心誠意、開拓に部落発展に力を尽くした」と郷土史に書かれており、開拓功労者として表彰されています。
その後、農地貸下げは昭和16年まで、ほぼ毎年行われ、総面積は1633.9531ヘクタールにものぼります。
|
|
|
地域の方からのお話
|
【Nさん】
●開拓前の麓郷はもちろん森でしたので、高く太い木が沢山はえていたそうです。しかも機械などはなく、全て人力でやっていて開拓までの道のりは険しかったのです。やっとのことで木を切り倒しても問題は山積みでした。そのひとつが畑が作れないことです。畑には大きな石がいっぱいあって耕す事などできなかったそうです。でも毎日毎日作業を続けようやく今のような、広く大きな畑ができた。とおっしゃっていました。ご協力ありがとうございました。
【Mさん】
●その昔、麓郷には水道がありませんでした。井戸を掘って飲み水を得ていました。
Mさんは、麓郷の山から湧き出る水をそのままの形で多くの人に飲んでもらえないか、と考えました。しかし、当時の麓郷の人々は貧しく、水道を引く工事を他に頼む余裕などありませんでした。
「よし、それならオレが作ってみよう!!」
Mさんは土木工事の専門家ではありませんでしたが、直感的にこの工事はできると確信したそうです。はじめは誰も話を聞いてくれなかったそうですが、工事が始まると多くの人が協力金を出してくれました。やがて水が出たときにはみんな泣いて喜んだそうです。
この話を倉本聡先生が聞いて、ドラマ「北の国から」の中に引用したそうです。また、麓郷中学校もこの水を飲んでいます。
(写真 取材の様子。右がMさん)
 |
(開拓の足どりend)
|
|
| 2. 幻の森林軌道 |
|
昭和3年。布部~麓郷間に森林軌道が完成しました。それまでは、馬そりと川に流しての流送でしたが、鉄道が作られて大変便利になったのです。原木が集まって来るところは、現在の石の家のあたりで、そこから布部までの間に鉄道がありました。
調べてみると、同じような森林軌道は東山地区にもありました!広い東大演習林の中を、2本の鉄道が走っていたのです。東山の森林軌道は、下金山までありました。
昭和26年。開基30周年の頃に「岩屋」の切り替え工事が行われました。この土木工事によって、現在の麓郷街道が完成されました。岩屋のところに、「開基30周年記念」という石碑が建っています。また、この道路の完成によって、森林軌道が廃止されることになってしまいました
森林軌道には、客車がついていて、病人や用事のある人を乗せてくれました。夢のある森林軌道・・・再び、つくってほしいです。
私たちは、東麓郷のKさんの案内で、森林軌道の跡地を自転車で回りました。10年ほど前までは、鉄道の跡地がわかる所がいっぱいあったそうですが、今では全くわかりませんでした。とっても、残念だったです。
|
|
|

森林軌道が出来た頃の麓郷市街の様子です。左側の建物は、農協です。 |

在りし日の森林軌道
木材のほか用事のある人を布部まで運んでくれました。当時は自転車を持っていれば大そうなお金持ち、という時代。森林軌道の功績は大きかったことでしょう。 |

東大演習林麓郷作業所
現在は「森林資料館」として、内部を改装して利用されています。
|
(幻の森林軌道end)
|